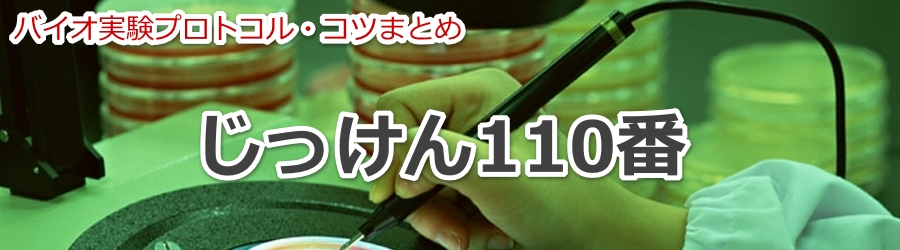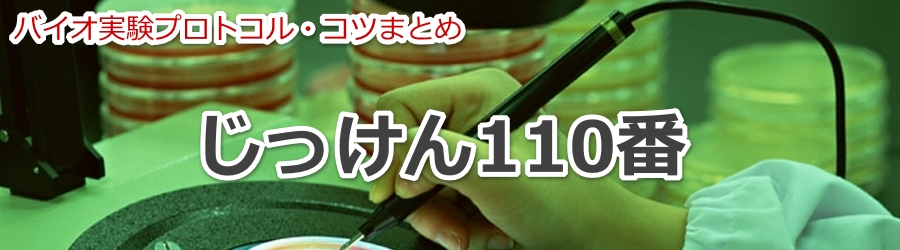培養細胞の免疫染色(ICC; immunocytochemistry)のプロトコルを紹介します。
ラボによって使用する試薬や濃度が違いますが、それぞれの作業の順序や目的は共通しているはずです。
ここでは、サイト作成者である私が主に用いている方法を紹介します。
準備試薬
- PBS
- 固定液:4%パラホルムアルデヒド(PFA)/PBS (WAKO #163-20145) 4℃保存
- Wash buffer: 0.025% Tween 20/PBS (250uLの10% Tween20+100mLのPBS) 常温保存
- Blocking buffer: 10% 正常血清/ 0.3% Triton X100/PBS (300uLのTriton X100+100mLのPBSを常温保存し、用時調整で正常血清とこのバッファーを1:9で混合)
正常血清は、使用する2次抗体の作成動物由来のものを用います。(ヤギの場合が多いです)
プロトコル
ステップ1
- 培地を除去する
- 4%PFA/PBSを加え、室温で10分間反応
- Wash bufferで5分×3回の洗浄
- ここでPBSを加え、4℃でしばらく(1週間程度)保存可能
ステップ2
- Blocking bufferを加え、室温で20分間反応
- Wash bufferfで5分×3回洗浄
- Wash bufferで希釈した1次抗体を加える
- ウェルの大きさに切ったパラフィルムを上にかぶせる
- 4℃でオーバーナイト反応
ステップ3
- Wash bufferで5分×3回洗浄
- いきなりパラフィルムをピンセットで取り出すのではなく、まずWashbufferをパラフィルムの上から加え、パラフィルムを浮かせてからピンセットでつまんで取り除くようにすると、細胞を傷つけにくい。
- ヘキスト(DAPI)を1:2500、2次抗体を1:400で希釈したwash bufferを加え、室温で1時間反応
※希釈率は最適な条件に変更すること。
- Wash bufferで5分×3回洗浄
- 培養プレートのまま顕微鏡観察する場合、PBSを加えた状態で観察。プレパラートを作成したり、スライドチャンバーの場合は、それぞれ必要な処理をしてから観察。
どこに細胞培養するか?
- 培養プレートに普通に培養した細胞を免疫染色・・・蛍光顕微鏡で観察したときに、フォーカスが甘くなって綺麗な画像が得られにくい。対物レンズ10Xより倍率が高いとかなり不鮮明になる。
- 培養プレートの底に丸いカバーガラスを敷き、そこに細胞を培養させ、免疫染色後にカバーガラスを取り出し、反転させてプレパラートを作成する・・・高倍率でも鮮明な画像が観察できる。ただし、カバーガラス上だと細胞の生着率が悪くなりがちなので、その点は工夫を要する。
- チャンバースライドを使う・・・高価
チェックすべきポイント・トラブルシューティング
バンドのおおよその分子量で真偽の判断のつきやすいウェスタンブロッティングと違い、免疫染色のシグナル(蛍光)は偽陽性や非特異的反応との区別が難しく、画像データの解釈にはより慎重な判断が必要です。
- 1次抗体あり、2次抗体なしのサンプルが発色していないか?→自家蛍光の可能性
- 1次抗体なし(もしくは1次抗体の代わりにアイソタイプIgG)、2次抗体ありのサンプルが発色していないか?→2次抗体の非特異的な反応による偽陽性反応の可能性
- 1次抗体も2次抗体もなしで蛍光を発していないか?→自家蛍光の可能性
- 検出するタンパク質の局在位置(核内or細胞質or細胞膜)が正しいか?
培養細胞の免疫染色の結果を解釈するうえで有用な参考文献(pdf)
「データを正確に解釈するための6つのポイント」シリーズ・蛍光顕微鏡データの誤った解釈