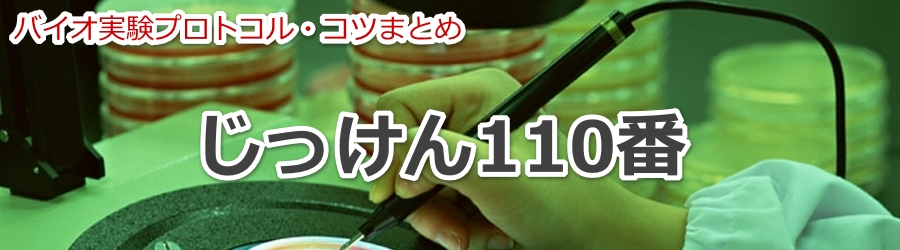
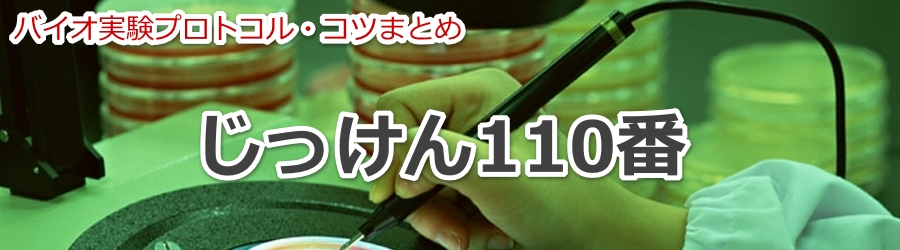
このページにはプロモーションが含まれています。
忙しくても利用しやすい理系学生・院生特化型就活サイト
マウス・ラットがトレッドミルでうまく走らない場合の対処法
バイオ実験でマウスやラットの運動能力・持久力を測定する場合にトレッドミルで走らせることがあります。
ですが、動物の扱いに慣れていない場合、なかなかトレッドミルで走ってくれない、ショックグリッドの上から動かない、と困ってしまう人も少なくありません。
聞いたところでは、3匹いれば1匹は走らないヤツが出てきて毎回困っている・・・なんて人もいるようです。
実は、マウスやラットをトレッドミルでスムーズに走らせるには、ほんのちょっとしたコツがあり、それさえ守れば、ほぼ100%スムーズに走らせることができます。
事実、この文章を書いている私自身、これまで何十匹も走らせてきましたが、走らなかったものは一匹もいません!
それでは、マウス・ラットをスムーズに走らせるためのプロトコルをご紹介します。
- トレッドミルを静止させ(傾斜はあってもなくてもよい)、グリッドには通電させた状態にします。
- 最初は最低速度(1m/min)でベルトを動かします。
- マウス(ラット)は最初は走らないと思います。
ベルトによって徐々にグリッドのほうに動いていき、グリッドに触れるとショックを感じて逃げます。
もし逃げないようであればショックが弱すぎます。 - 以後2分おきに一段階ずつ速度を上げていきます。
その間、マウスは「逃げる」→「止まる」→「ベルトによってグリッドのほうへ移動する」→「グリッドに触れる」→「逃げる」を何回か繰り返します。 - このサイクル中、2分おきに一段階ずつ速度を上げることを続けます。
すると、10m/minに達するころにはマウスはスムーズに走るようになっています
(ちなみに、10m/minはまだまだ軽いジョギング程度の速度です)。 - トレッドミルをストップさせ、15分程度休憩させます。
- その後、本番のトレッドミル走を開始します。
この方法はいきなりマウスを走らせずに、動いているかいないかのベルト速度で、マウスが気付かないうちにソロソロとグリッドに近づけるという点がポイントです。
マウスたちは最初はショックグリッドが何たるかを全く知らないわけですから、まずは「あれに当たればショックを感じる」ということを覚えさせるのです。
その後、少しずつベルトの速度が上がっていく中で、マウスたちは床が動いていること、止まっていればグリッドに近づいていくくと、反対方向に移動し続ければグリッドに当たらないことを学習していきます。
一旦これらのことを学習させてから、本番に入るのです。
ポイントは焦らずじっくり時間をかけて(といっても20分ですが)トレッドミルに馴らしていくことです。
いきなり速度を上げないことです。
動いているか、いないか、というくらいの速度から始めることです。
動物が走らないという方は、大抵、いきなりそこそこの速度で走らせようとしています。
これでは、マウスがパニックになってしまい、状況を学習できません。
とにかく、焦らずにジワジワと馴らすことが大事です!
とはいっても、実際のところ、賢い個体は、ここまで時間をかけなくても学習します。
大丈夫なようなら、1分おきに速度を上げても良いですし、10m/minに達する前に終わっても良いかもしれません。
ですが、一応プロトコルは毎回一定にしておいたほうが良いので、私は毎回2分おきにしています。
トレッドミルQ&A
基本的には上り坂のほうが良いと思います。
というのも、水平の状態で限界まで走らせる場合、ベルトの速度が上り坂に比べて速いスピードにまで達します。
あまりに速いスピードになった場合、マウスの体力の限界で走れなくなるというよりも、脚の回転がベルトのスピードに追い付かずに走れなくなるように感じられるからです。
ただし、比較したい群間で体重差が大きい場合は一考を要します。
上り坂走の場合、体重の重いマウスはいわば「重い荷物を背負って山登りしている」状態になるからです。
この場合、走力の差は体力(持久力)の差だけでなく、体重差が大きな要因となる可能性があります。
水平走の場合には、体重による影響は少なくなると考えてよいでしょう。
通常、下り坂走を行わせる実験は行いません(実際、トレッドミルを下り坂に設定できないものも多い)。
しかし、下り坂走をさせることで、脚の筋肉に強い負荷を与え、人間でいう筋肉痛と同じ状態を作ることができます。
筋肉の再生の研究などでは、下りのトレッドミルを行う場合もあります。
