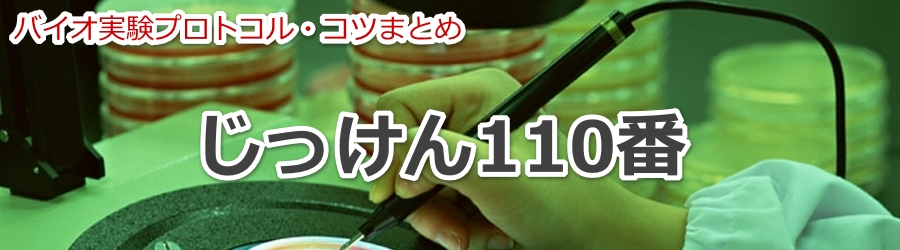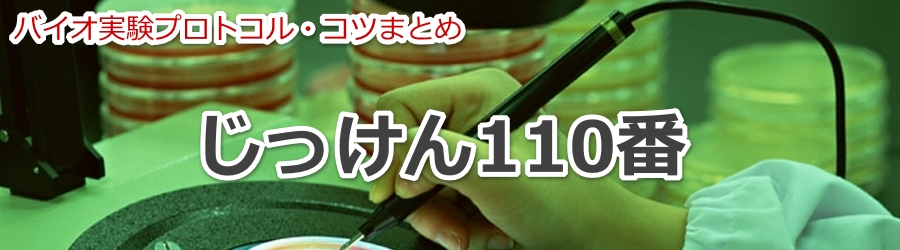MTTアッセイは培養細胞の生存率や増殖率を調べる実験で、通常96ウェルのプレートを利用して行われます。
このプロトコルや実験のコツ・注意点について解説します。
準備試薬
- MTT溶液:PBS50mLに対し250mgのMTT(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide M2128 Sigma)を溶かし、滅菌フィルターに通す。
-20℃、遮光保存で数か月間保存できる。
- MTT溶出液:イソプロパノール(2-プロパノール)50mLに対し、0.2mL 1M HCl、50uL Nondet P-40(NP40)を溶かす(最終濃度 4mM HCl,0.1% NP40)。室温保存。
MTTアッセイ プロトコル
- 96ウェルプレートに細胞を播種する。
このとき、アッセイする日にコンフルエントにならない程度の細胞数にすること。
ブランクとして、細胞を播かない空のwellも作っておくこと。
- 細胞の培地を新しいものに交換する
(必須ではないが交換するほうが望ましい。特に、薬剤投与をしている場合はその薬剤がMTTの染色に影響を与える可能性が無きにしもあらずなので)。
培地の量は1ウェルあたり100uL。ブランクにも培地を加える。
- 培地を捨てず、ウェルごと(ブランクも)に20uLのMTT溶液を加える。
- CO2インキュベーターにプレートを戻し、3.5時間インキュベーションする。
- 細胞をはがしてしまわないように、注意して培地を捨てる。
(私の場合、大まかに培地を捨てた後、机にキムタオルを重ねて敷き、そのうえでプレートを下向きにひっくり返した状態で軽くキムタオルに叩きつけて培地を除去している)
- MTT溶出液を各ウェル(ブランクも)ごとに150uLずつ加える。
プレートをアルミホイルで遮光する。
- シェーカーで30分間シェークする。
ここでしっかり混ぜ、全ての色素を溶出させること。
さもないとウェル内でムラができて吸光度が正確に測定できない。
(シェークが十分かどうか、測定前に目で確認したほうが良い)
- マイクロプレートリーダーで590nmの吸光度を測定(バックグランドには620nm)
各ウェルの吸光度からブランクの吸光度を引いた数値が結果の数値となる。
なお、上記プロトコルはこちらを参考にしています。
MTTアッセイ解析方法
- 単に生細胞数を評価する場合は、Y軸に吸光度を示すケースが多い。
- 毒性のある薬剤に対する細胞の生存率を評価する場合は、controlの吸光度を1として、処置群の吸光度を%で表し、生存率とする。
- 96wellプレートを複数枚用意しておき、1枚目は播種24時間後に染色、2枚目は48時間後、3枚目は・・・というように細胞数の変化を経時的に追っていくことも可能。
コツと注意点
- MTTで染色する時点で細胞がコンフルエントにならない程度の数に細胞を撒くこと。
初めての場合は予備実験などで決めておくこと。
- 96wellと小さいウェルのため、各ウェルに培地を加えた後に必要数の細胞を加えるという方法だと、細胞数の誤差がウェル間で大きくなる。
あらかじめ必要な細胞数を必要量の培地に懸濁してから、その懸濁液を各ウェルに添加する手順のほうが良い。
- 初代培養などで高い血清濃度の培地を用いる場合、上手くできない場合がある。
私が経験した範囲では、30%FBSでは不可能で、10%FBSでは可能であった。
高濃度血清が必要な実験系の場合、アッセイ当日の培地交換で10%FBSの培地に変更する。
MTTアッセイの原理
MTTが生細胞に取り込まれ、ミトコンドリア内の還元酵素によって還元されて不溶性のフォルマザンになる。
界面活性剤入りの希塩酸によってフォルマザンを可溶化し、呈色した溶液の吸光度を定量することで細胞増殖の程度を評価することができる。
補足
ミトコンドリア酵素活性を失った死細胞では染色されない。生細胞のみ染色される。
また、細胞の代謝の状態によって、同じ細胞数でも吸光度が変わってしまう可能性はないわけではない。
よって、厳密にいうと、吸光度が生細胞数をそのまま反映しているわけではない。
例えば、細胞数には影響を与えないが、ミトコンドリア活性を非常に高める薬剤を加えた場合、細胞数は同じだが吸光度は高くなる、という可能性だってある。
細胞数を実際に数えているわけではなく、あくまで生細胞数と良い相関関係を示すフォルマザンの吸光度を測定しているにすぎない。
しかしながら、実験手技としては簡便であり、また測定well数を増やすことでバラつきの少ないデータになるのでよく用いられる。
再現性を確認するために、1度のアッセイで済ますのではなく、3回程度同じ実験を繰り返し、同じ傾向になることを確認するべき。